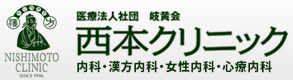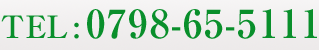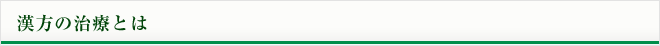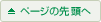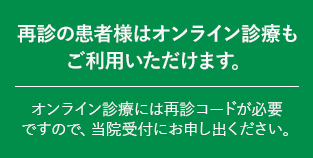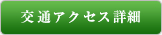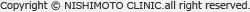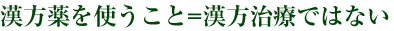
 さて、いよいよ診断です。「聞診」「望診」「問診」「切診」から得られた情報を総合(四診総合)して、気血のめぐりや問題のある臓腑、病気の状態・原因を特定し、治療方針を導きだすことを、漢方では「弁証」といっています。
さて、いよいよ診断です。「聞診」「望診」「問診」「切診」から得られた情報を総合(四診総合)して、気血のめぐりや問題のある臓腑、病気の状態・原因を特定し、治療方針を導きだすことを、漢方では「弁証」といっています。
こうした診断による結果は、まさに十人十色。たとえ、西洋医学的に同じ病名でも、全く違う治療方針が立てられることになります。これが、漢方でいう「
例をあげてみましょう。春になると、鼻水やくしゃみ、目のかゆみなど、同じような症状が現れる患者さんが二人いたとします。西洋医学的な検査でアレルゲン(アレルギーを起こす原因となる物質)を調べた結果、二人ともスギ花粉にアレルギーがあることが分かりました。この場合、西洋医学では、ステロイドや抗ヒスタミン剤、抗アレルギー剤などの薬で症状を押さえたり、アレルゲン抽出液を少しずつ投与することで抗体を作る「減感作療法」などの治療が行われます。病院によっては、『小青竜湯』などの漢方薬を対症療法的に出す場合もあるかもしれませんが、いずれにしても、「スギ花粉症」という病名に基づいた治療です。
しかし、漢方の場合は、「花粉症」という病名から薬を選ぶことはありません。同じ病名がついていても、この二人の体質や病態には必ず違いがあるからです。四診によって、鼻水の量や粘り方、目の赤みやかゆみの有無はもちろん、胃腸の調子はどうか、冷え性か、精神状態はどうか、といったきめ細かい情報を得て、その人の体にいちばん合った漢方薬を処方することになります。また、シーズン外であれば、体質的な問題点を解決して、花粉に対する抵抗力を養うといった治療も可能です。
このように、花粉症という病名は同じでも、治療方針や処方は人によって全く違ってきます。このことを考えれば、漢方薬というのは、単独で存在するものではなく、漢方的な理論や診断の結果、導きだされる「答え」に過ぎないということが分かると思います。そのため、たとえ同じ『小青竜湯』という薬が処方される場合でも、漢方理論に基づいて出される場合と、西洋医学の現場で対症療法的に用いられた場合とでは、意味合いが全く異なるわけです。
もうひとこと付け加えるなら、「花粉症に効く」という触れ込みの健康食品やお茶も、体に合わなければ全く意味がありません。薬でも食べ物でも、誰かに効いたものが他の人にも効くわけではないということは、ぜひ覚えておいて欲しいものです。

「同病異治」と表裏一体となった考え方に、「
例えば、疲労感、下痢、胃下垂、不正性器出血など、一見なんのつながりもない症状が同時に出ている場合でも、漢方的にみると「いずれも、脾胃の気が不足したために引き起こされた症状」という結論が出ることがあります。この場合、脾胃の気を補う処方を用いれば、どの症状も一緒に治していくことができます。
もちろん、実際の症例はこれほど単純ではなく、問題点が多岐にわたっていたり、特につらい症状だけ先に治すという方法をとることもあります。しかし、この場合にも「異病同治」の原則は活きており、最終的に体全体のバランスが整えば、すべての症状は自然に消失します。
また、特に「異病同治」を意識していなくても、皮膚病の治療をしている患者さんに「最近、便秘が治ったような気がするんですが」といわれたり、腰痛の人に「漢方薬を飲み始めたら、どういうわけか目がよく見えるようになりました」などと不思議がられることがあります。漢方治療の現場ではよくあることで、これこそが、体のバランスを整えていく漢方治療の醍醐味といえるかもしれません。もちろんこれも、その人の体にきちんと合った薬を飲んでこそ。「○○は万病に効く」といった話とは、全く別物であることはいうまでもありません。
「異病同治」の法則は、自律神経失調症やホルモンバランスの失調など、「不定愁訴」が出やすいときの治療にも役立てることができます。
例えば、更年期障害で、ほてり、イライラ、発汗、息切れ、動悸などの不定愁訴がある場合、西洋医学では、それぞれの症状に対する薬を出すしかないのが現状です。最近では、「ホルモン補充法」が注目され、臨床的にもかなりの効果をあげていますが、肝機能に障害が出る可能性があること、子宮筋腫や乳腺症の経験者、乳ガンや子宮体ガンの人が家系にいる場合には不向きであるなど、デメリットが大きい方法であることも否めません。
漢方とて、更年期のさまざまな症状を100%治せるわけではありませんが、体の歪みのおおもとを見極めることで、つらい症状をとりのぞきつつ、自然な老化へと導くことも可能なのです。

 先ほど、「花粉症も、シーズン外であれば体質的な問題点を解決して、花粉に対する抵抗力を養う治療が可能」という話をしましたが、ここには、漢方的な対症療法(
先ほど、「花粉症も、シーズン外であれば体質的な問題点を解決して、花粉に対する抵抗力を養う治療が可能」という話をしましたが、ここには、漢方的な対症療法(
漢方の場合、花粉症のシーズン中であっても、対症療法だけを行うわけではありません。例えば、胃腸の機能が低下が原因で、花粉症の根本原因である「水毒」がたまっているようなら、胃腸の機能を高める治療を行います。ただ、これだけでは、花粉症の症状であるくしゃみ、鼻水、鼻づまりといった症状を抑えることはできません。鼻の症状は、五臓のうちの肺と関係が深いため、肺にある熱や冷えをとりのぞくという「対症療法」を併用することになります。このように、根本治療と対症療法を組み合わせた治療法を、漢方では「
もちろん、漢方の場合、対症療法ではあっても、体質素因をないがしろにするようなことはありません。鼻水が透明で水っぽく、冷えなどの症状を伴うときには『
シーズン外の治療が有効な理由は、こんなところにあります。「敵」のいないオフシーズンであれば、じっくりと気血のめぐりや五臓の調和を整えることができるのです。もちろん、アレルギーという遺伝的な要因まで治すことはできませんが、後天的に体の中で作られてきた「体の環境」を変えて、花粉に負けない防衛力を身につけ、症状が出ないようにすることは十分に可能です。また、症状が現れた場合も、かなり軽くすむ場合が多いので、対症療法の効き目も高くなります。
このように、根本治療と対症療法を組み合わせた治療ができるからこそ、漢方は慢性病にも急性病にも幅広く対応していくことができるのです。なお、ここでいう対症療法とは、単に症状を抑えることではなく、目の前にある問題をとりあえず解決するという意味も含みます。
根本治療と対症療法のどちらに重点をおくかは、病気の程度や体の状態によって決められます。例えば、健康な人が風邪をひいた場合には、発汗させてウイルスを追い出す、という対症療法のみで治すことができますが、気というエネルギーが不足している人の場合、汗をかかせるだけでは、ますます防衛力を低下させることになりかねません。かといって、気を補う薬だけを使うと、体が気をもらさないように毛穴をきゅっと引き締めてしまうので、「泥棒が部屋にいるのに、カギを締めた」ような状態になってしまいます。上手に風邪を治すためには、「泥棒だけを追い出し、素早くカギを締める」ことができるよう、根本治療と対症療法の兼ね合いが必要になってくるわけです。 s
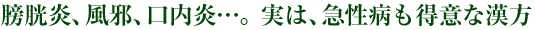
これまで、漢方の風邪の治療については何度か紹介してきましたが、このほかにも漢方治療が適する急性病はたくさんあります。
例えば、膀胱炎。抗生物質や抗菌剤で簡単に治すことができるため、単発性のものなら特に漢方にこだわる必要はありません。ただ、女性の中には、かなり頻繁に膀胱炎を起こすという人もいます。そのたびに抗生物質を飲むことに抵抗を感じる人もいるでしょうし、西洋医学では膀胱炎の再発を防ぐ有効な手立てもありません。その点、漢方なら、急性時の治療はもちろん、再発防止や、排尿時の痛みや違和感などの後遺症まで幅広く対応することができます。
西洋医学の現場でも、『猪苓湯』を対症療法的に使うことはよくありますが、急性時に適応する漢方薬は他にもたくさんあります。『
このほか、急性の胃痛や下痢、口内炎、夏バテ、じんましん、皮膚のかゆみ、目の疲れなど、日ごろ気になる症状のほとんどが漢方の適応症といえます。また、症状が軽度であれば、薬ではなく、食べ物やツボ刺激など、セルフケアの方法も充実しているのが漢方の大きな特徴です。
ただ、「何が何でも漢方」という考え方も少々危険。特に、腹部の強い痛みや、激しい下痢などは、悠長に構えていると命にかかわることもあります。緊急を要する症状かどうか、自分で冷静に見極め、「これはまずい」と思ったときには、すぐに検査や緊急処置ができる西洋医学の病院に駆け込む、といった心構えも必要です。
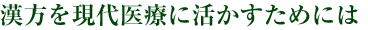
漢方薬を用いるときには、漢方の理論や診察が不可欠、という話を何度かしてきましたが、このあたりで、漢方薬に対する西洋医学と漢方の考え方を整理してみましょう。
西洋医学は、伝染病の撲滅など、華々しい過去をもつ一方で、「予防医学」への取り組みはほとんど行われていませんでした。つまり、「病気になったら治す」ということに重点を置き、病気になりにくい体を作るという発想は、つい最近になるまで皆無に等しい状況だったのです。
これに対して、体内の「陰陽」や「虚実」のバランスを整えて、気・血・水がスムーズにめぐることを治療の目標としている漢方では、積極的に病気になりにくい体を作る医学ともいえます。ともすると、漢方は過去の医学で、西洋医学こそが現代医学ととらえられがちですが、こと予防医学に関しては、いつの時代も漢方が一歩先を行っていたのです。 健康問題が、伝染病のような急性病から慢性病へと変化した現在、西洋医学の「病気になったら治す」という発想だけでは、とうていすべての病気にうまく対応することはできません。そこで、今度は予防医学の先端を行っていた漢方に、再び目が向けられることになったわけです。
しかし、残念なことに、西洋医学が注目したのは、漢方の理論や診察法ではなく、漢方薬そのものでした。よく、漢方薬を西洋医学の理論のもとで用いることを、「相撲取りが野球をさせられるようなもの」とたとえることがありますが、まさに現状はその通りといえます。もちろん、力士の中にも野球が得意な人がいるように、西洋医学のルールのもとで効果をあげる漢方薬もあります。漢方薬の成分が科学的に分析され、その結果、悪性腫瘍やC型肝炎など、根治が難しい病気の治療薬として活躍することもあるでしょう。しかし、そのような用いられ方だけでは、漢方薬は本来の力を発揮できないのも、また事実なのです。 漢方の理論や診断法を知らない医師たちが、「漢方でも出しておけば気休めになるだろう」と、メーカーから勧められた処方をたいした根拠もなく使い、場合によっては、誤用で重要な副作用が起こることも十分あり得ます。記憶に新しいところでは、『小柴胡湯』を慢性肝炎の患者に投与し、死亡者が出たというニュースがありましたが、これも、漢方を知らずして漢方薬を使ったための不幸な結果といえます。 『小柴胡湯』は「めぐらせる」働きが強い薬であり、気・血・水ともに衰弱している慢性肝炎の患者に用いると、少ない気・血・水を無理やりめぐらせ、ますます消耗させることになります。これが、どれほど危険なことであるかは、漢方の立場からみれば明らかで
す。また、小柴胡湯を使う目安として「胸脇苦満」、つまり両脇部が張って苦しいという症状があり、腹診をすればすぐに確認できる、という基礎知識さえなく処方している西洋医学の医師も多いようです。
本来、予防医学的な治療を得意とする漢方と、すぐれた検査技術と切れ味のよい薬を武器にもつ西洋医学は、お互いのルールさえ理解できれば、十分に補完しあうことができる医学です。複雑化する一方の病気に立ち向かうためには、現代医療にも、漢方の診断法や理論といった「こころ」を活かしていくことが必要といえるのではないでしょうか。

 ではここで、ふだんの生活の中で、西洋医学と漢方をどのように使い分けていけばいいのかを少しお話しすることにしましょう。
ではここで、ふだんの生活の中で、西洋医学と漢方をどのように使い分けていけばいいのかを少しお話しすることにしましょう。
健康な人でも、たまには風邪をひいたり、おなかをこわすこともあります。このような日常的な症状は、できるだけ体に余計な負担をかけずに治すことが大切です。その意味では、常に体のバランスを考えながら治療する漢方が最適といえます。ただし、先ほど述べたように、症状がひどいときには、西洋医学の病院で検査や治療を受けることも必要です。
また、胃透視検査や超音波検査を含む健康診断も、一年に一度は受けておいたほうがいいと思います。先日、ある患者さんに「健診とは、その時点で病気ではないことを証明するもので、その翌日にガンができないという保証はない」といわれて、なるほどそうだ、と思いもしたのですが、胃や大腸、それに子宮などのガンは、早期に見つければほぼ100%治る時代です。そういう意味でも、やはり定期的な健診を受けることをおすすめします。
では、例えば「胃の調子が悪い」など、日常的な症状でありながら、危険な病気の兆候ともとれる症状にどう対応すべきかを考えてみましょう。西洋医学的な検査を受けて、腫瘍などがないことを確認してから、漢方の治療を受けるという方法が理想ですが、胃の調子が悪いときにバリウムや胃カメラなどの検査はつらい、というのであれば、まず漢方の診療を受けるという方法もあると思います。私の場合、このような症状の患者さんに対しては、まず漢方的な診察を行い、漢方薬を処方しますが、それで調子がよくなった場合でも、薬をやめて一定期間おいてから、もう一度来院してもらうようにしています。このときにまた調子が悪くなっているようなら、やはり検査を勧めることになります。
ただ、いつでもこれほどスムーズに段取りが進むとは限りません。例えば、「血圧がかなり高いけれど、降圧剤だけは飲みたくない」「漢方薬なら、糖尿病の特効薬もあるのではないか」などと駆け込んでくる患者さんもいます。
高血圧や糖尿病などの成人病は、漢方の治療を併用することで、薬の量を減らしたり、食餌療法や運動の効果を高めることは可能ですが、西洋医学で治りにくい病状のときは、やはり漢方でも治すのが難しいケースが多いのです。それだけに、両者が手を組むことが大切であり、また、本人の自己管理が不可欠になってきます。そのため、「漢方薬を飲んでいるから大丈夫」と、食事や運動などによる自己管理を放棄したり、西洋薬の服用を勝手にやめてしまう、といった行為は非常に危険です。
漢方治療が有益といっても、食餌療法や運動の代わりになるわけではありません。高血圧や糖尿病は、自己管理が何より大切な病気であること、ある程度進行した場合には、西洋医学的な治療が不可欠となることをよく理解して、上手に病気と付き合って欲しいと思います。

漢方で病気を治すとき、必ずしも漢方薬を使うとは限りません。鍼やお灸、気功といった方法もありますし、症状が軽くなってきた場合は、食餌療法や運動など、生活指導だけですむこともあります。
漢方の食餌療法の大きな特徴は、症状が現れている「部分」をみるのではなく、体全体のバランスを整えていくという方法をとるという点です。つまり、漢方薬か、食べ物かという違いはあっても、根本的には同じ漢方理論から導きだされているわけです。
仮に、健康診断で慢性胃炎と高脂血症が同時にみつかったとしましょう。この場合、西洋医学では「胃に負担をかけないように、消化の悪い繊維質は控えめに」「高脂血症を悪化させないためには、繊維質を積極的にとることが大切」と、相反する指導がなされることもあります。しかし、漢方の場合は、慢性胃炎と高脂血症という症状も、ある種の「歪み」、あるいは「体の声」ととらえ、全体のバランスを整える食事指導をしますので、矛盾が生じることもありません。「『病』をみる西洋医学、『病人』をみる漢方」といわれるゆえんも、このあたりにあるといえるでしょう。
では、漢方の食餌療法の考え方をもう少し詳しく紹介することにしましょう。漢方の食餌療法は、病気の治療食(食療)と、健康維持のための食養生である「食養」に大きく分けられますが、ここでは、日常生活の中でも活用できる「食養」について詳述したいと思います。
漢方の食養生などというと、薬臭いイメージをもつ人がいるかもしれません。もちろん、漢方薬の材料である生薬を使った料理もありますが、そういうものを食べることだけが食養生というわけではないのです。例えば、朝食のメニューをパンと牛乳にするか、それともご飯とみそ汁にするかを体質や体調に合わせて選ぶのも、食養生のひとつといえます。
つまり、ここでもいちばん大切なのは、「体が欲している食べ物は何か」「おなかはちゃんとすいているか」といった体の声に耳を傾け、自分の体と対話することなのです。これからお話しすることも、体とコミュニケーションをとるための手段と考えれば、分かりやすいのではないかと思います。
食養生も、「気・血・水」「五臓」「八綱」といった漢方理論が基本となります。この中でも、日常生活に取り入れやすいのは、「寒熱」の考え方です。
漢方薬に体を温めるものと冷やすものがあるように、食べ物もまた「温・熱」、「涼・寒」といった性質をもっています(第三章の「食べ物の寒熱表」参照)。食べ物の性質や、調理法による変化を知っておけば、「体のバランスがちょっと崩れているようだ」と思ったときにも、食べ物である程度調整するということができるようになるはずです。
例えば、冷たい雨に濡れて、体が冷えきってしまったとき。温かい紅茶に、体を温めるショウガやシナモン、カルダモンなどのスパイスを加えて飲めば、すぐに体がぽかぽかしてくるはず。また、食事の献立を考えるときにも、「今日のメインのカニは体を冷やすから、サラダはやめて煮物にしよう」「冷たいものを飲み過ぎたようだから、昼ご飯はニラとネギの雑炊でおなかを温めよう」といった発想の転換ができるようになります。
また、体を温めたり冷やしたりという薬効は、体の歪みを治す場合には便利ですが、健康な人が寒熱のどちらかに偏った食べ物ばかりとっていると、逆に体のバランスを崩す原因になってしまいます。実際、サラダやジュース、アイスクリームなどの多食で冷え性になってしまったり、お酒や香辛料のとりすぎで体によぶんな熱がこもってしまうなど、偏食によって体調を崩す人は案外多いのです。やはり、健康維持のための食事は、バランスがとれていることがいちばん大切なのです。ちなみに、和食の中心的存在である米は、寒にも熱にも偏らない「平性」で、胃腸を丈夫にするという薬効もあります。そういう意味でも、米は主食に最適な食べ物といえるでしょう。
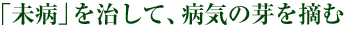
 元気をなくしてしまった観葉植物は、放っておけば、いずれ葉が落ちて、枝が干からび、最終的には根までもが枯れてしまいます。でも、早いうちに水や栄養を与えたり、日光に当てたりといった処置をすれば、ちゃんともとの元気を取り戻してくれます。
元気をなくしてしまった観葉植物は、放っておけば、いずれ葉が落ちて、枝が干からび、最終的には根までもが枯れてしまいます。でも、早いうちに水や栄養を与えたり、日光に当てたりといった処置をすれば、ちゃんともとの元気を取り戻してくれます。
人間も同じで、「病気というほどではないけれど、ちょっと具合が悪い」という状態のまま放っておくと、体の歪みがだんだんと大きくなって、やがては「病気」へと発展してしまいます。
この「ちょっと具合が悪い」という段階を重視し、積極的に治療していこうというのが、漢方の「未病みびょうを治す」という発想です。
気滞、オ血、水毒といった余剰物質の問題、五臓のちょっとした機能失調などは、漢方的な診察をすれば分かりますが、西洋医学的な検査では発見することができません。極端な話、たとえ人間ドックで問題がなくても、「未病」、つまり半健康状態という可能性はあるのです。もちろん、だからといって人間ドックが無意味というわけではありません。これといった症状もなく進行する早期ガンのように、西洋医学的な検査では発見できても、漢方の診察ではみつけにくい病気もたくさんあるからです。
この「未病を治す」ことの重要性をよく言い表しているのが、『黄帝内経』にある「病気になってから治すのは、のどが渇いてから井戸を掘るのを思いつき、戦争になってから武器を作るのと同じではないか」という話です。西洋医学からみれば、「病気になっていない人は治すことができない」ということになるかもしれませんが、これは、「健康体」というもののとらえ方の違い、つまり、検査で異常がなければ健康体とみなす西洋医学と、肩こりや便秘など、病気として認められていない症状も「未病」ととらえる漢方の違いといえるでしょう。
このように、病気の発生の前段階を重視する漢方には、「四次元的な発想」があるとみることもできます。つまり、病気が表面化した「現在」を三次元的にとらえるだけでなく、病気の発生とかかわりのある「過去」や、治療や養生によって変化する「未来」といった時系列的な面までもとらえることができるのです。
実際の診療でも、現在の状況だけをみて、「あなたの体質はこうです」「このような病状です」と説明するのは、ある意味では簡単なことです。しかし、「未来」の健康を視野に入れた治療を行うためには、その人の「過去」、つまり、今までの生活習慣と病気とのかかわりを説明し、納得してもらうことが大切なのではないかと考えています。
それでは、もう少し漢方の治療について具体的に知っていただくために、身近な症状の治療例をあげて説明していくことにしましょう。