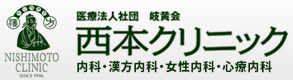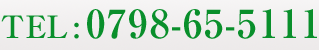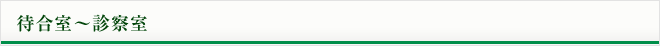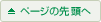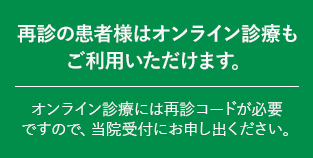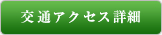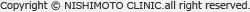皆さんは、「漢方の治療」に対して、どんなイメージをもっているでしょうか。
皆さんは、「漢方の治療」に対して、どんなイメージをもっているでしょうか。
漢方専門医がいない病院でも漢方薬を使うことはありますし、薬局でも漢方薬は売られています。しかし、漢方薬を使うことイコール漢方治療とはいえないのです。
では、漢方の専門家がいる病院・医院では、どんな病気や症状を、どのように治療しているのでしょうか。
漢方治療というと、「慢性病をじっくりと治す」というイメージを抱く人が多いようです。確かに、西洋医学とは異なる視点をもつ漢方は、慢性病や成人病の強い味方ですが、だからといって、急性の病気に不向きというわけではありません。
例えば風邪などは、そのときの症状や体質にぴったり合った薬を使えば、西洋薬よりずっと早く治すことができます。しかも、強い薬で症状を抑え込むようなことはせず、体のバランスを調和するという方法で治していくため、体に歪みを残すこともありません。また、肩こり、便秘、体のだるさ、冷えなど、西洋医学では病気と認められないような症状も、「体の悲鳴」ととらえて治療するという考え方は、日常医療にぴったりといえます。
二千年以上もの歴史をもつ漢方は、理論だけでなく、診察方法もまた西洋医学とはかなりの違いがあります。聴診器もレントゲンも、血液検査もなかったころ、医師は自分たちの五感を鋭くして、目や耳、手を使って、体の中の情報を得ようとしました。こうしてできあがったのが、漢方の「四診」という診察方法です。
四診とは、聞診(耳で聞く)、問診(病状について質問する)、望診(目で見る)切診(手で触る)の四つのこと。特に、望診の中の「舌診」と、切診の中の「脈診」「腹診」は、漢方独特の方法といえるでしょう。
このような漢方的な診察を行うことで、検査数値には表れない微妙な異変も察知することができます。そういう意味からも、四診はすぐれた診察法ではありますが、胃や腸の中を直接のぞいたり、心電図をとったりする西洋医学の検査は、また別の意味があります。そのため、現代の漢方医療の現場では、西洋医学的な検査データも参考にしますし、必要と思われる場合は新たに検査を受けてもらうこともあるのです。特に初診時は、悪い病気が隠れていないかどうかのチェックが必要になるため、「漢方医」も「内科医」に頭を切り替えて、西洋医学的な見地からの診察も行います。
さて、それでは、実際にはどんな診察や治療が行われるのか、当クリニックを例にして、漢方診療の疑似体験をしていただきましょう。
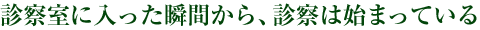
誰でも、初対面の人と会うときには、話しやすい人かどうか、自分と合いそうなタイプ かなど、いろいろな感情をもって接すると思います。
これは、診察室の中でも同じです。初診のときに、あなたが「この医者は話をちゃんと聞いてくれる人だろうか」「症状や気持ちをきちんと理解してくれる人だといいな」などと考えるように、医者のほうでも、これからお付き合いを始める人として、「性格は明るそうな人だ」「ずいぶん元気よくドアを開けて入ってきたな」など、病気には直接関係ないことを観察したりもします。
医師と患者の出会いは、人と人との出会いでもあります。このことに、西洋医学も漢方もありませんが、漢方の場合の「観察」には、それ以上の意味があります。患者さんの表情、顔色、肌のツヤ、足取り、眼光、姿勢などを観察することは、「望診」という重要な診断材料でもあるのです。
見た目による体調の判断は、医者と患者という関係だけでなく、日常的にも行われているものです。具合が悪いとき、家族や会社の同僚に「顔色が悪いよ」「だるそうにみえるけど、どこか悪いの?」などと心配された経験は、誰にでもあることでしょう。「望診」では、そういった一般的な判断はもちろん、「皮膚や髪にツヤがなく、顔色も白っぽい。血虚の傾向がありそうだ」「目の下がぷくっとふくれているのは、水毒のせいかもしれない」といった漢方的な診断も同時に行っています。また、話す声の力強さや、呼吸の様子、痰がからんだようなせき払いをしていないか、など、「音」による「聞診」も、体質素因や体調などを判断する目安になります。
ちなみに、『黄帝内経』には、「脾胃(消化器)が弱い人は顔色が黄色く、肺が弱い人は白く、腎が弱い人は黒い」など、顔色と臓器の関係について書かれています。検査機器などなかった時代の「望診」は、今よりずっと重要な意味があり、また、当時の医師というものは、見たり聞いたりするものから、体内の情報を読み取る達人だったに違いありません。
検査技術の進んだ現代において、主観の入った「望診」や「聞診」にどれほどの意味があるのか…と疑問視する声もありますが、検査とて完ぺきなものではないこと、また、診断を下すのはあくまで人間であることを考えれば、どんなに小さなことにも目を凝らし、耳をそばだてることは、今も昔も診察の基本といえるのではないかと思っています。
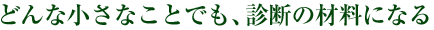
漢方の初診は、だいたい15〜20分かかるのがふつうです。そのほとんどの時間は、 「問診」に費やされます。
まずは、待合室で書いてもらった「問診表」に目を通して、質問をしていくわけですが、このとき必ずしも主症状に関する質問から入るわけではありません。
症状が現れている「部分」だけでなく、全体をみる医学である漢方では、体のすべての症候が関連しあっていると考えています。そのため、頭痛を訴える患者さんに「こむら返りはありませんか」と聞いたり、花粉症の人に髪の毛の状態を尋ねる場合もあるわけです。 また、尿や便の状態、女性の月経などは、非常に大切な情報源であるため、たいていの人に質問します。「答えにくいことをどうしてしつこく聞くのだろう。私の症状とは関係がないのに…」などと思わず、正直に、気楽に答えるようにしてください。
なお、問診は、医師と患者のリレーションシップの場でもあります。どんなささいなことでも、気軽に相談するべきですし、また、話をきちんと聞いてくれる医師を選ぶことも大切なことだと思います。
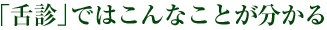
 漢方の診察を始めて受けるとき、いちばん驚くのは「舌をみせてください」といわれる ことでしょう。
漢方の診察を始めて受けるとき、いちばん驚くのは「舌をみせてください」といわれる ことでしょう。
「舌でいったい何が分かるというのだろう」と不思議に思うかもしれませんが、舌には実にさまざまな情報が隠されています。試しに、毎日の変化を観察したり、他の人の舌と比べたりしてみてください。「暴飲暴食が続いていて、ちょっと胃腸の調子が悪いと思っていたら、舌に白い苔のようなものがべったりついていた」「冷え性の私の舌より、暑がりの夫の舌のほうが赤みが強い」といったことに気づくはずです。
このように、舌自体の色・形(舌質)や舌苔を観察することで、「寒熱」の区別や、気血のめぐり、水毒やオ血など病理物質の種類、病気がこれから悪くなるところなのか、それともよくなりかけているのか、といったことまでが分かります。また、舌の先は心、側面は肝、舌根部は脾や腎、といった具合に、部位による五臓の診断も行うことができます。
ときどき、歯を磨くときに、一緒に舌苔までこそげ落としてしまうという人がいますが、舌苔の有無や状態は、全身の健康をチェックする目安になりますので、自然のままにしておいたほうがいいでしょう。また、漢方の診察を受ける前には、コーヒーや紅茶、飴など、舌に色がついてしまうものの飲食も避けるべき。正確な診断を妨げる原因になるからです。
なお、ふだんの健康チェックに役立つポイントをあげておきますので、参考にしてください。
【舌質】
●きれいなピンク色(正常舌)
ふっくらと柔らかく、舌全体がきれいなピンク色で、適度な湿り気を帯びている。
●舌全体の赤みが薄く、白っぽい
気血が不足している人や、体が冷えに傾いているときにみられる舌。髪や肌にツヤがなく、疲れやすい、貧血を起こしやすい、などの症状を伴うことも。
●舌全体が暗紅色
血のめぐりが悪いときにみられる舌。舌の裏の静脈や、顔、唇なども紫がかった暗紅色であることが多い。紫色の斑点(オ斑、オ点)が舌につく場合もある。肩こり、頭痛、冷え、生理痛などの症状が出やすい。
●紫色の斑点がある
紫色の斑点(オ斑、オ点)は、オ血を表している。
●舌の色が全体的に赤い
体が熱に傾いていると、血管が拡張して舌の色も赤くなる。舌の先だけ赤いのは、「心」に熱がこもっている証拠。
●舌の縁に歯のあとがついている
水分代謝が悪くなると、舌もむくんで歯型がつきやすくなる。胃腸の消化機能が低下している人や、水分をとりすぎている人によくみられる。気の不足を伴うことも。
●舌に亀裂が入っている
もともと舌に亀裂がある場合は問題ないが、急に舌がひび割れたような状態になったときは、ストレスや過労の影響で、陰虚(潤い不足)になっている可能性がある。
【舌苔】
●薄く白い苔(正常)
苔舌は、舌そのものの色が透けてみえるくらいの薄さが正常。色は薄い白が正常で、よぶんな熱があると色が濃く(黄色っぽく)なる。
●白くべったりとした苔
食べすぎや消化吸収力の低下で、水毒などの余剰物質が体内に生まれると舌苔が厚ぼったくなる。胃腸の冷えを伴うことも多い。
●黄色くべったりとした苔
色が薄黄色で厚さも薄い場合は、ほぼ正常。体の中の水毒が化熱すると、黄色くべったりとした苔になる。
●苔がほとんどなく、乾燥ぎみの舌
苔がほとんど消失して、舌全体の潤いが少ないのは、陰虚の舌。相対的に熱が生じている場合には、舌全体が赤っぽく(深紅色)なる。
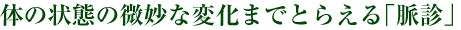
西洋医学でも脈をとることはありますが、脈拍数を数えたり、不整脈がないかどうかを確認する程度です。これに対して、漢方の「脈診」には、非常に大きな意味があります。
脈の打つ力、血管壁の硬さ、脈が触れる深さなどをチェックすることで、病気の性質や勢い、病気に対する抵抗力、臓器の調和状態、気血の流れなどを調べることができるのです。
女性の場合は、月経の前か後かというだけでも脈は変わりますが、特に変化が大きいのは妊娠したときです。たいていは、脈が強く元気に打つようになり、玉が転がるような「滑脈かつみゃく」という脈象が表れます。生命力が旺盛な胎児がおなかに宿ることによって、母体の気血が充実してきた証です。
また、脈の性質(脈象)は体の状態によって変化するため、注意深く観察していると「風邪をひきかけているな」「いつもよりイライラしているようだ」といったことまで判断がつくようになります。「どうして分かるんですか」などと驚かれることが多いのですが、慣れてくれば自分でもある程度は分かるようになるものです。例えば、熱が出ているときには脈が速くなりますし、元気が出ないときには、脈もなんとなく沈んでいるように感じるはずです。
実際に脈をみるときには、「六部定位」といって、左右それぞれ三個所ずつ、計六ヶ所の脈を調べます。いちばん手首寄りを「寸」、真ん中が「関」、ひじ寄りを「尺」と呼び、それぞれの部位が臓器と関連していると考えています。ちなみに、右は主に機の寸から順に、右手は肺、脾、腎、左は心、肝、腎との関連が深いとされています。また、漢方では脈象を28種類に分類していて、糸がピンと張っているような緊張の強い脈は「弦脈」、脈が糸のように細い「細脈」など、それぞれに名前がついています。

 おなかの診察にも、漢方独特の方法があります。西洋医学では、肝臓や脾臓に触れたり、おなかに腫瘍がないかどうかを探すことが主になりますが、漢方では、おなかを押さえたときの抵抗や、押したときの痛み方などで、気血の流れや充実度、内臓の状態を判定することができるのです。
おなかの診察にも、漢方独特の方法があります。西洋医学では、肝臓や脾臓に触れたり、おなかに腫瘍がないかどうかを探すことが主になりますが、漢方では、おなかを押さえたときの抵抗や、押したときの痛み方などで、気血の流れや充実度、内臓の状態を判定することができるのです。
例えば、胃腸の機能が弱いと、おなかを押しても抵抗があまりなく、ふにゃふにゃと柔らかい感じがします。また、下腹部を押して痛みが走るのは、血の滞りである「オ血」の表れですし、みぞおちのあたりを押したときに、ポチャポチャと水音がするのは体内によぶんな水がたまっている(心下停水)証拠です。
また、押すと痛みが増す場合(拒按)は、「水毒」や「オ血」、あるいは感染などによる「実」の痛みであることが多く、押して気持ちよく感じる場合(喜按)は、胃腸の機能が低下しているという判断法もあります。よく、胃腸の調子が悪いときに、何気なく胃やおなかを押さえていたり、寝るときにおなかを布団にぴったりとくっつけるような姿勢をとってしまうことがありますが、いってみれば、これも「喜按」の一種といえるでしょう。
なお、腹診は消化器の調子を見極めるだけの診察法ではなく、体全体の情報を得る手段のひとつです。そのため、たとえ皮膚や耳、鼻などの病気でも、初診の際には必ず行います。